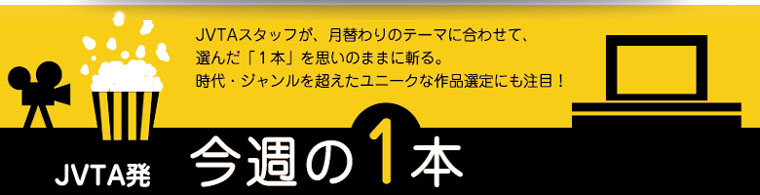vol.47 『Sex and the City』シーズン2 最終話、そして『追憶』 by 潮地愛子
12月のテーマ:節目
今や、日本にも数え切れないほどの『Sex and the City』ファンがいるだろうが、私もその1人だ。
アメリカで映画版が公開初日を迎えた時は、ちょうどLA出張中だったので、現地スタッフに頼んで劇場まで送ってもらい、真夜中0時の第1回上映を堪能した。もちろんシーズン1~6までのボックスセットは持っていて、防水仕様のDVDプレーヤーでお風呂に入りながら鑑賞するのが日課のようになっている。
ちなみに先日、十何度目かのシーズン4に突入したところである。その時々の自分のおかれている状況によっても感じ方や見方が違ってくるせいか、何度見ても飽きない。めちゃくちゃベタな言い方だが、本当によくできたドラマだと思う。
中でもいちばん好きなのが、シーズン2の最終話だ。
昼間のバーで4人がカクテルを飲んでいる。そして時を同じくして、同じ街で主人公キャリーの別れた恋人、ビッグの婚約パーティーが開かれている。
なぜ彼は自分を選ばなかったのかと問うキャリーに、ミランダが一言、「ハベルだから」と言う。
ロバート・レッドフォードが『追憶』で演じたハベルのことだ。ハベルはバーブラ・ストライサンド演じる情熱的な女性ケイティと恋に落ち、結婚にいたるが、結局は別の女性を選ぶ。キャリーの解釈によれば、女にはケイティのような複雑な性格をした女と、単純な女の2種類がいる。彼女はケイティのようなタイプだから、ビッグは彼女を理解しきれなかったというのが結論だ。
キャリーたちは『追憶』のクライマックスシーンを再現したあと、主題歌の「The Way We Were」を合唱する。
Can it be that it was all so simple then
Or has time rewritten every line
If we had the chance to do it all again
Tell me - would we?
Could we?
あの頃、すべてはそう単純だったかしら
それとも、時がすべてを書き換えてしまったのかしら
もし、やりなおすことができるとしたら...
ねえ、そうする?
やり直せるかしら? (「The Way We Were」より一部抜粋)
3人と別れたあとの帰り道、キャリーはビッグに会う。彼女はケイティのごとく彼の髪をなでて言う。"Your girl is lovely, Hubble." (彼女、すてきねハベル)。
そして、"I don't get it"(分からないな) と首をかしげるビッグに、"You never did"(あなたは私を理解できなかった)と言い放って去っていく。
キャリーがビッグと結ばれないことに胸がしめつけられながらも、彼女なりのふんぎりをつけ、前を向いて歩いていくキャリーのたくましさに感動を覚えずにはいられない。
そして、このシーズン2の最終話を味わうためにも、ぜひ『追憶』を見てハベルとケイティを知ってほしい。また、キャリーたちが再現するラストシーンと実際のラストシーンを比べてみて、微妙な違いに気づくのもちょっと楽しいかもしれない。
「The Way We Were」の歌詞にあるように、過去を振り返って、やり直せたらどんなにいいかと思うことが誰にでもあるだろうと思う。私にはたくさんある。でも、泣いても叫んでも時間を巻き戻すことはできないし、それどころか、時間は私になんておかまいなしに確実に過ぎていき、気づけば2009年がやってこようとしている。キャリーとケイティばりに、前を向いていくしかない。
─────────────────────────────
『Sex and the City』
出演:サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、
クリスティン・デーヴィス、キム・キャトラル 他
製作:ダレン・スター
製作年:1999年(シーズン2)
製作国:アメリカ
『追憶』
出演:バーブラ・ストライサンド、ロバート・レッドフォード 他
監督:シドニー・ポラック
製作年:1973年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────