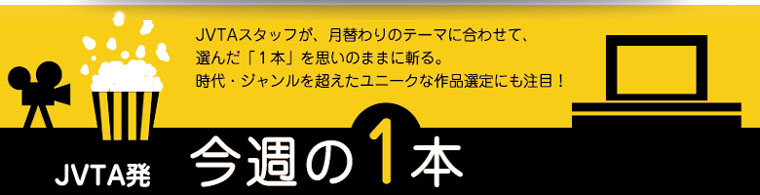5月のテーマ:旅
翻訳者は言葉が持つニュアンスに敏感であるべきだ。例えば"旅"と"旅行"という単語の意味、定義について考えてみる。辞書においては、旅は「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行」とあり、旅行は「徒歩または交通機関によって、おもに観光・慰安などの目的で、他の地方に行くこと。旅」となっていて、ほとんど違いはない。では、なぜ修学旅行を"修学旅"、放浪の旅を"放浪の旅行"とは言えないのか?それは言葉の持つニュアンスが存在するからだ。旅にはどことなく"自由"というニュアンスがあり、旅行には"計画性"のようなものが含まれている気がする。同じ「他の地方に行くこと」にしても"気まま"とか"行き当たりばったり"がなければ、それは旅ではなく旅行だし、すべてにおいてきちんと仕切られた旅は旅行と呼ぶべきではないだろうか。今回は旅映画と呼ぶにふさわしい"気まま"や"行き当たりばったり"満載の作品を紹介しようと思う。
『ストレンジャー・ザン・パラダイス』
ニューヨークに住むウィリーのアパートに、ある日、故郷ハンガリーからいとこのエヴァが訪ねて来る。アメリカでの生活を送るため、クリーブランドに住むおばの家へ行く予定だったエヴァを、おばが急きょ入院することになったため、しばらくの間預かることになったのだ。最初はギクシャクするウィリーとエヴァだが、やがてウィリーの友人エディーを交えた奇妙な友情が芽生えていく。やがて、おばの回復に伴いクリーブランドに旅立ったエヴァ。一年後、急に思い立ったウィリーとエディーは、エヴァと再会を果たすべくクリーブランドへと車で出発する。
派手なセットもなく、セリフも少ないうえ、淡々と進む物語だが、どことなくコミカルで、ほのぼのとした雰囲気が漂う本作。ストーリーはすべて思いつきと行き当たりばったりで展開されていく。旅に出るウィリーとエディーには計画性のかけらもなく、イカサマポーカーで巻き上げた金で、思いつくや否やクリーブランドへ出発。突然の訪問に驚くエヴァを誘い、今度は思いつきでフロリダへ。もちろん理由などない。そしてフロリダでは負けた時のことも考えず、有り金すべてをギャンブルにつぎ込む。いい加減でだらしないとも言えるが、彼らには気持ちいいほどの自由と不思議な生命力が溢れている。観るたびに、ふらりとどこか遠くへ旅したくなる作品だ。
最近待望のDVD化を果たしたジム・ジャームッシュの初期作品たち。不朽の名作『ダウン・バイ・ロー』と共に、是非チェックしたい一本だ。
─────────────────────────────────
『ストレンジャー・ザン・パラダイス』
出演:ジョン・ルーリー、エスター・バリント
監督:ジム・ジャームッシュ
製作年:1984年
製作国:アメリカ/西ドイツ
─────────────────────────────────
4月のテーマ:花
昔、ある男の子がこんなことを言っていた。
ある女友達の家に行ったら、花瓶に花が活けてあった。それまでその子の
ことを異性として意識したことなんかなかったのに、その花瓶の花を目撃
してからというもの、彼女のことが気になってしょうがない。
このあと2人の間に恋が芽生えたのかどうか... は置いておくとして、
「花」には人の心を動かす、ちょっぴり特別な力があるに違いないと思う。
子どもの頃、ピアノの発表会で花束をもらえば、ウキウキして気分よく
ピアノが弾けたものだし、一人暮らしの家で気分が浮かない夜を過ごした
翌朝、テーブルに何気なく飾っていた一輪の花を見て、ちょっと前向きな
気分になれたなんてことも。ケンカしたガールフレンドのもとに、
ボーイフレンドが大きな花束を抱えていくシーンなんて、よく映画にも
出てくるけど、彼女は彼の両手いっぱいの花を見た瞬間、一気にすべてを
許せてしまうんじゃないだろうか。
『マルタのやさしい刺繍』のマルタは、小さな花の刺繍で人生を変えた。
スイスの小さな村に住む80歳のマルタは、最愛の夫に先立たれたあと
生きる気力を失っていた。毎夜、夫の遺影を胸に抱いてベッドに横たわり
朝が来なきゃいいのにと思いながら朝を迎えてため息をつく日々。
ところがある日、長年忘れていた若かりし頃の夢を思い出した時から
マルタの日常は輝きを取り戻し始める。その夢とは、自分でデザインして
刺繍をした、ランジェリー・ショップをオープンさせること。
保守的な村では、マルタの夢は冷笑され軽蔑されるばかりだったが
一度覚悟を決めたらマルタは強かった! 3人のおばあちゃん友達に支え
られながら、マルタは自分の夢実現のためにコツコツ努力を重ね、物語の
最後には村中の人々に受け入れられる。
これでもかというほど保守的な村で、80歳のおばあちゃんが一番進歩的な
夢を語りそれを叶えるなんて、笑っちゃうぐらいさわやかで鮮やかだ。
ちなみにこのスイス映画、英語タイトルは『Late Bloomers』。
人生の「花」を咲かせるのは、その気にさえなればいつだってできるのさ!
なんてちょっと照れるけど、マルタを見てると、ついつい熱い気持ちに
なってしまう。
今日はいつもより遠回りしてお花屋さんに寄ってしまおう、かな。
───────────────────────────────────
『マルタのやさしい刺繍』
出演:シュテファニー・グラーザー、ハイジ・マリア・グレスナーほか
監督:ベティナ・オベルリ
製作年:2006年
製作国:スイス
───────────────────────────────────
4月のテーマ:花
「無人島に1本だけ映画を持っていくなら?」ともし聞かれたら、『ミツバチのささやき』と答えようと思っている。ほかにも好きな作品はあるけれど、無人島で繰り返し繰り返し見る作品となると選択肢はそれほど多くはない。
『ミツバチのささやき』の舞台はスペイン内戦時代の田舎町。アナという幼い少女は姉のイザベルと一緒に、町にやって来た新作映画を見にいく。真っ暗な映画館で子供たちと肩を並べるアナ。スクリーンには、科学者フランシュタインの手で造り出された怪物の姿が映し出される。
やがて怪物は偶然、1人の少女に出会う。少女は恐ろしい形相をした怪物に近づき、「一緒に遊ぼう」と言って花を渡す。怪物は初めて自分に示された愛情に顔をほころばせる。だが少女と一緒に花を湖に投げて遊ぶうち、怪物は思わず少女を湖に放り込んでしまう。少女の死によって民衆の怒りをかった怪物は、風車小屋に追い込まれ火を放たれる。
アナが見るこの映画『フランシュタイン』(1931年)は、怪奇映画の傑作として名高い作品だ。なかでもこの少女と花で遊ぶシーンは、名シーンの1つに数えられる。
だがその結果訪れる怪物の悲しい運命を目にしたアナは、姉のイザベルに問いかける。「どうしてあの怪物は少女を殺したの? どうしてみんなはあの怪物を殺したの?」。
まだ幼いアナの世界には「内側」と「外側」の境界は存在しない。生と死、空想と現実、恐れと喜びはすべてひとつのものにすぎない。そんなアナはこの2つの死が理解できず、問いを繰り返す。そしてやがてアナは、この映画との出会いから現実と空想の世界に迷い込み、『ミツバチのささやき』は水辺での怪物と少女の邂逅を想起させるシーンで幕を閉じる。
『フランシュタイン』を見た人は、アナの問いかけに対して「所詮は怪物だから」と答えるかもしれない。「怪物は人間には理解しがたい感情で少女を殺し、民衆は自分たちと相容れない存在を排除しようとしただけなのだ」。
だが、その答えでアナは納得するだろうか? もし自分たちとは異なる存在が「怪物」なのだとしたら、偏見のないまなざしで世界を見つめるアナにとって、何が怪物で、何が怪物ではないのだろうか? 怪物に花を手渡し、そして殺された少女の生まれ変わりとも言えるアナは、見る者にこう問いかけてもいるのかもしれない――「誰が怪物なの?」と。
─────────────────────────────────
『ミツバチのささやき』
出演:アナ・トレント、イサベル・テリェリア
監督:ヴィクトル・エリセ
製作年:1973年
製作国:スペイン
─────────────────────────────────
3月のテーマ:出会い
"朝に嗅ぐナパームの匂いは格別だ"
『地獄の黙示録』で、ロバート・デュヴァル扮するキルゴア中佐が、敵兵の潜むジャングルを焼き払った際に言った名セリフだ。僕が、この映画を観たのは小学生の頃だったと思うが、幼い僕の心には鮮烈な印象が残された。とはいっても、映画の内容などよく分かっていなかったし(ちなみに、いま観てもよく分からない...。)、映画そのものに感銘を受けたわけではない(ちなみに、それは今でも同じ...。)
僕の心を捉えたのは、ズバリ音楽だ。
キルゴア中佐率いる武装ヘリ師団が敵の村へ向かい、攻撃を仕掛けるシーンで、僕はワグナーの「ワルキューレの騎行」に出会った。この曲が流れてきた瞬間、僕は急いでラジカセを持ってきて、テレビから流れてくる音を必死に録音し、その後、文字通りテープが切れるまで聞き込んだ。クラシックの荘厳な曲調に乗せて、眼下に広がる海岸線を抜けて敵に向かって突進する無数の武装ヘリ...。そのシーンの意味することなど何も分からなかったが、聴くたびに情景を思い出し、胸を躍らせていたものだ。
つくづく、映画と音楽の相乗効果には驚かされる。
たとえば、カヴァレリア・ルスティカーナを聞けば、『ゴッドファーザーPART III』のラスト、陽の当たる道を歩きたいと願い、必死に這い上がろうとしたものの、ついに果たせなかった男が迎える哀しい人生の終末がまざまざと頭に浮かぶし、『ジョーズ』のテーマを聞けば、何か禍々しい事態が近づいていることを連想する。
最近、映画を観て、こんな経験をすることが、あまりにも少ない気がする。それは、サントラ音楽の選定に主な原因があるのではないかと思う。ロックやポップスをサントラに使うのが、最近ではすっかり定番になっているが、たいていの場合、映像との相乗効果が得られないのだ。ほんの一例だが、『ブラックホーク・ダウン』でも武装ヘリが敵地に向けて飛ぶシーンがあり、間違いなく『地獄の黙示録』へのオマージュなのだが、このシーンは全然心に残らない。なぜなら、フェイス・ノー・モアというバンドの曲が使われているからだ。フェイス・ノー・モア自体はいいバンドだと思うが、やはり、映画にはオーケストラで奏でられるクラシックやオペラのアリアこそふさわしいと思う。
ところで、幼少のころに「ワルキューレの騎行」に深く感銘を受けた僕は、そのままクラシック音楽に傾倒するのかと思いきや、幸か不幸かヘビーメタルという音楽に出会い、そちらの世界に行ってしまった。本来ならば、AC/DCやメタリカの代わりに、バッハやモーツァルトのCDが山積になっていたかもしれないのに...。
─────────────────────────────────
『地獄の黙示録』
出演:マーロン・ブランド、マーティン・シーン
監督:フランシス・フォード・コッポラ
製作:フランシス・フォード・コッポラ
製作年:1979年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────
3月のテーマ:出会い
ダブリンの街中で友達とコーヒーショップで暇つぶしをしていた時、What is life ? と聞かれたことがある。その時20代前半だった私は、その問いに即答することができなかった。たいして旨くもないコーヒーをすすりながらしばらく考えてみたけれど、気のきいた答えなどちっとも思い浮かばなかった。「人生なんて、ひとことで言い表せるもんじゃないよ」と私が言い訳をすると、彼女は言った。「そんなことないって、もっとシンプルだよ。私にとっては、Life is a choice.なの」
私よりいくつか年上の彼女がとてもオトナに思えたことを今でも覚えている。
そして、人生経験を重ねるにつれて、彼女の言ったLife is a choice. を実感することが多くなった。
人生には選択がつきまとう。私が今ここにいること。それは数々の選択の結果に他ならない。流されているつもりでも、思うようにいかなように見えても、結局は何気ない小さな選択の積み重ねの結果だったりするんじゃないか。そして、人生の選択につながる重要なファクターが「出会い」なのじゃないかと、この頃考えている。
誰と出会うか、何と出会うか。望んでいても、望んでいなくても。行き着く先が分からなくても。出会いは人生を左右する。ただ、右にいくか、左にいくかは、結局your choice なのだ。
何年か経って、彼女と再会した。当時、彼女は夫と離婚の話し合いを進めていた。彼は家を出て、新しい恋人と暮らしているということだった。結婚当初、彼はまだ学生だったので、生活を支えていたのは彼女だった。だが、彼が就職して生活が安定してから、彼女はずっと専業主婦だった。離婚となっては仕事を探さねばならない。彼女は言わなかったけれど、職探しは順調ではないようだった。シングルマザーで生活を支えていかなければならないことに苦労している様子がうかがえた。
もちろん夫婦の間にはいろんなことがあるのだろうし、私がとやかく言えることではないけれど、私は彼女の夫に対して腹立たしい気持ちでいっぱいだった。そんな私の心のうちを察したのか分からないが、彼女は言った。
「後悔してない。出会った頃、彼のことが本当に好きで、まるで『恋におちて』みたいだった。人生であんな思いを味わわせてくれた彼には、本当に感謝しているの」
そして、夫が新しい恋人に対してあの頃の私のような思いを抱いているんだろうなって、客観的には理解できるのよね、と言って彼女は笑った。
私は何も言えず、旨くもないコーヒーをすすりながら彼女の話を聞いていた。感覚を失ったかのように、何も感じることができなかった。そんなことを言えてしまう彼女に、ただただ圧倒された。
「恋におちて」をDVDレンタルショップで見かけて手にしたのは、彼女との再会を果たしてしばらくしてからだったと思う。
「恋におちて」はロバート・デ・ニーロ演じる妻子ある男フランクと、メリル・ストリープ演じる人妻モリーの恋物語だ。2人は偶然の出会いから恋に落ち、プラトニックな関係を続けていく。だが、結局はほころびが見えていたそれぞれの結婚生活には終止符が打たれる。
そして映画は、お互いを忘れられない2人の再会によりハッピー・エンドで終わる。
確かに、相手を思い続ける2人の愛は純粋で美しいのかもしれない。でも、私はこの映画を好きにはなれなかった。多分それは、愛している相手が他の人に心を奪われていくモリーの夫やフランクの妻の哀しさに、胸を打たれてしまうからなのだと思う。もちろん人の気持ちは無理に変えることはできないけれど、この映画で描かれる純粋で美しいとされる愛が、去られた者に残すのは、時に残酷で醜いものだったりするのではないか。
それでもすべては結局、それぞれの選択の結果に過ぎないのかもしれない。残酷で醜いものを残されてしまうことも含めて。いや、だけど・・・。
まだまだ、私が未熟なのだろうと思う。もっといくつもの選択を重ねて、いつかこの映画を観たら、異なる想いを抱くことができるのかもしれない。
彼女とは、あれ以来会っていない。でも、たいして旨くもないコーヒーをすする羽目になるたび、彼女の言葉を思い出す。そして、彼女がどこかで幸せにやっていることを願うのだ。
─────────────────────────────────
『恋におちて』
出演:ロバート・デ・ニーロ、メリル・ストリープ
監督:ウール・グロスバード
製作:マーヴィン・ワース
製作年:1984年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────
2月のテーマ:ビター&スイート
少し前の"発見!今週のキラリ☆"で、桜井くんが"味"をテーマにステキなコラムを書いていたが、味覚というものは年齢を重ねるに従い変化する。僕の場合、特に実感するのは、子供の頃、食べるくらいなら飢え死にしたほうがマシだった苦い食べ物、ピーマンや魚のワタ(内臓)などが、今となっては大好物であることだ。そういった変化は映画の好みにも見られる。子供の頃はいわゆる"ハッピー・エンド"で分かりやすい、ハンバーグやオムライスのような映画が好きだった。弱者をいたぶる悪党をカッコイイ正義の味方がやっつけるヒーローものや、美しい女性に恋をし、振られながらも追いかけ、最後は振り向いてもらえる恋愛ドラマなど、不安があったとしても、どこかしら希望が持て、「きっと最後は大丈夫だよね」的な、エンディングが予測できる"甘い映画"が好きだった。また、年齢を重ね二十歳くらいになると、歴史モノ、特に戦争をテーマにした作品や、人種問題を扱った社会派ドラマなどの"辛い映画"をよく見た。そして、ここ数年は今日紹介するような"苦い映画"にハマっている。
『ノーカントリー』
舞台はアメリカのテキサス州。溶接工のモス(ジョシュ・ブローリン)は偶然、ギャング同士の麻薬売買がこじれたであろう、抗争現場に遭遇する。死体が転がる中、札束の入ったカバンを奪い、逃走を図るモスだが、ギャング組織の追っ手、シガー(ハビエル・バルデム)に命を狙われる羽目に。シガーは冷酷で無慈悲な殺人マシーン。執念深いことこの上なく、逃げるモスをコンピューターのような正確さで追い詰めていく...。
コーエン兄弟の作品は苦い。「ファーゴ」や「バーバー」、「バートン・フィンク」などもそうだが、絶えずブラックなユーモアや皮肉、不条理が作中にお香のように立ち込める。見終わった後に清々しさや安堵の気持ちなどは微塵も残らない。登場するヒーローは必ずしも強くないし、善人が必ずしも幸福ではない。悪党が生き残り、正直者が馬鹿を見る。歯がゆいし、悔しい。でも世の中を正視すれば、それは事実であり、決してウソではないことに気づく。身近な所で起こっていることを見ても分かる。昨日まで働いていた職場を一瞬で解雇され、公園で寝起きするサラリーマン。泥酔状態で国際会議に出席する大臣...。矛盾や不条理が溢れている。ただし、コーエン兄弟はそこで卑屈にはならない。みんなが目を背けたくなるものをギリギリと噛み締め、搾り出した苦汁を堆肥のように撒き散らし、世間をあざ笑うのだ。
─────────────────────────────────
『ノーカントリー』
出演:ハビエル・バルデム 、ジョシュ・ブローリン他
監督・脚本:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン
製作:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン
製作年:2007年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────
2月のテーマ:ビター&スイート
先週、札幌で行われたキューバ映画祭に行ってきました。
還暦を迎えた雪祭りに沸く北の町札幌で、カリブ海の真珠キューバの映画。
こたつでアイスを食べるような幸福感につつまれて、5本の映画を鑑賞しました。
今回取り上げる作品『苺とチョコレート』は、恐らく日本でもっとも有名なキューバ作品。
映画祭でももちろん上映しました。
舞台は1980年代のキューバの首都ハバナ。1959年以来現在も続く革命政権を支持する大学生ダビドは、恋人に裏切られたばかり。ある日、人気のアイスクリーム店「コッペリア」でチョコレートアイスを食べていると、向かいに苺のアイスを持ったディエゴが座る。
男のくせに苺アイスを食べるなんてゲイに違いない...。
警戒する一方で、ディエゴの文学話に好奇心をそそられるダビド。結局、自分の写真を持ってるという話につられて彼のアパートまで行くことに。部屋の中は芸術的な調度品や貴重な書籍、洗練された音楽で溢れていた。展示会に出すという友人の過激な彫刻作品。おまけに正規では入手できないはずの舶来もののウィスキー...。
ディエゴが反体制派であることを改めて確信したダビドは、同志のミゲルに事情を話す。性的指向といい、過激な趣味に展示会といい、危険因子とにらんだミゲルは、ディエゴをスパイするようダビドを促す。親しいふりをしてディエゴに接近するダビドだが、次第に2人の距離は縮まってゆき...
ダビドが男性に目覚める。
...という話ではありません。かといって政治思想に終始した話でもありません。
※ここから先、まるでレポートのように長くなってしまったので、偏見を持たずに作品を見たい方は先にまっさらな目で鑑賞されることをお勧めします...。
レイナルド・アレナス原作、ハビエル・バルデム主演の『夜になるまえに』をご覧になった方もいるでしょう。アレナスはキューバ出身の有名な作家で、同性愛者であることや過激な主張から迫害を受け、アメリカへの亡命を余儀なくされます。この作品でも描かれているように、キューバ政府が同性愛者に対し弾圧的な態度をとったということはしばしば取り上げられる話題です。
"ゲイ=反体制派" という式図は私たちにはあまりピンと来ない。自転車ライトをつけていない=窃盗車とみなされる時のような単純さと理不尽さを覚えます。ある種の傾向をもとに、政府は若いうちに芽をつんでいるつもりでしょうが、そのこと自体が相手をかたくなにしている。そのこと自体が反対派を作り出しているという矛盾があります。
それでも政府に権威となんらかの正当性を感じる限り、大抵の国民は盲目的に巻かれてゆく。
そんな中、文化面での抑圧を敏感に察知したディエゴは疑問を持つ。その鋭さ自体が、政府にとって脅威となるのです。
ディエゴは個人として、国に自由を求めました。国を愛するからこそ声を上げ、それを貫いたからこそ、不本意な結果にいたります。
この作品が他でもないキューバ政府の検閲を通ったなんて不思議に感じますが、少なくともディエゴは報われていない。中から描く限り、ある意味でこれは見せしめ的な効果を持っているようにもとらえられます。(監督の本意ではなく、検閲を通るための巧みなトリックとして)
アレナスの作品のような、自伝による外からの批判とは別の性格を帯びている。また、この作品を許すこと自体が政府の文化的寛容性を示すことになるようにも思えます。
ディエゴは、ダビドを愛するがゆえに彼からも身を引きます。社会でも否定され、恋心もかなわない。ディエゴの話しぶりはとってもスウィートでコミカルでユーモラスですが、その裏でどれほどの苦悩を抱えていたかと思うと本当に痛々しくなります。
一方ダビドは、革命のおかげで貧しくても大学に通えるという恩恵を受け、盲目的に政府を信じていました。しかしディエゴとの出会いによって個人の意思を取り戻します。政府を支持してはいても、疑問の余地があることを認めるようになる。恋人への失望も含め、若いダビドが成長してゆく過程も注目ポイントの1つです。ダビドは次第にディエゴに対しても心を開き、2人の関係は固い友情という形に昇華してゆきます。
2人の関係性は、もちろんキューバという国で、この特殊な状況があったからこそ生まれたものでしょう。2人を取り巻くすべての要素が2人の関係を築いた。でも何よりも2人が個人だったから、この絆が生まれたのだと思います。
取り巻く条件は違っていても、私たちだって社会との関係性や個人的な恋愛・友情の狭間で、一喜一憂して生きている。そういう意味ではすごく共感できる作品です。どんな映画にもどんな人生にもビター&スイートはあふれている。この作品はちょっぴり苦味が強いかもしれない。でもその中には、己の信念を貫いたからこそ味わえる格別のスイートが眠っているのです。
固いことばかり書きましたが、コミカルな要素やステキなセリフがあふれた素晴らしいドラマ作品です。見方も千差万別。私自身も次に観るとき(たぶん4回目)はまた別の発見があるはず。
字幕もとってもステキなので、ぜひ観てみてくださいね。
─────────────────────────────────
●『苺とチョコレート』
出演:ホルヘ・ペルゴリア、ウラジミール・クルス、ミルタ・イバラ 他
監督:トマス・グティエレス・アレア、フアン・カルロス・タビオ
脚本:セネル・パス
製作:ミゲル・メンドーサ
製作年:1993年
製作国:キューバ/メキシコ/スペイン
─────────────────────────────────
1月のテーマ:はじめての○○
恐らく皆さんも経験があるのではないかと思うのですが、アメリカのアクション映画を見ていると、たまにふと"香港映画的瞬間"に出会うことがあります。
余りにもスタンダード化が進んだため、最近はそれが"香港映画的"であることさえ思い出すのが難しくなってしまっているかもしれない、そんな"瞬間"です。
それらは時に格闘シーンに導入されるカンフーの要素であったり、銃撃戦のカット処理であったり、ワイヤーアクションの活用であったりするのですが、どの瞬間にも共通しているのは、運良く「これって香港映画っぽいかも」と気づいた時に体中に広がるあの不思議な高揚感でしょう。
そして私たちの"香港映画的瞬間"の記憶において、ひときわ輝いている存在が、今回紹介する『プロジェクトA』の監督・脚本・主演であるジャッキー・チェンです。
ある世代の映画ファンに特別な感慨を抱かせつつ昨年11月に休刊となった「ロードショー」誌の「好きな俳優ランキング」男優部門で1980年代に6年連続で第1位に選ばれ、読者に圧倒的な支持を得ていたこの香港出身の俳優/監督は、言葉の真の意味で、映画が生んだ偉大なアクションスターと言えます。
1984年に公開された『プロジェクトA』はジャッキー・チェンの監督・主演第4作として製作されました。
ジャッキー・チェン、ユン・ピョウ、サモ・ハン・キンポーの3人が主演スターとして初めて共演した作品であり、何を隠そう、当時中学生だった私が、学区内で初めて開店したビデオレンタル店で、初めて借りた作品です(確か1泊2日で700円。1週間レンタルというシステムは存在していなかった)。
多くのファンが躊躇なく彼のベスト1に推すこの作品が、そのオリジナリティとクオリティにおいて"ジャッキー・アクション"の集大成的な傑作であることは間違いないのですが、『プロジェクトA』は同時に、ジャッキー・チェンのフィルモグラフィの中でも突出したある特徴を持っています。つまり全編にちりばめられた直接、間接の映画的引用です。
有名な時計塔からの落下シーンには『ロイドの要心無用』でハロルド・ロイドがぶら下がったデパートの大時計が、海上警察と陸上警察が酒場で繰り広げる大喧嘩には『東京流れ者』で渡哲也が巻き込まれるストリップクラブでの乱闘シーンが、それぞれ直接的に引用されています。
また警察と海賊の両方から追われる身のジャッキー・チェンが、『北北西に進路を取れ』のケーリー・グラントばりに三すくみの状況を切り抜けたと思うと、上司の娘の手を引きつつキートンのように斜面をすべり降り、自転車と一緒にテラスから落下しそうになりながらもチャップリンのようにギリギリのところで持ちこたえる...。
アジア諸国やカンフー映画マニアの間ですでに絶大な人気を誇っていたジャッキー・チェンは、1987年にニューヨーク映画祭で『ポリス・ストーリー/香港国際警察』が特別上映されて以降、アメリカの映画関係者のあいだで評価を高めていきます。
この特別上映のきっかけを作ったのが他ならぬバート・レイノルズとクリント・イーストウッドだったのですが、彼らが初めて見て衝撃を受けたというジャッキー・チェンの作品は、映画祭で上映された『ポリス・ストーリー』と、『プロジェクトA』だったのです。
ブルース・ウィリスが命綱の消防用ホースを腰に巻き、ロサンゼルスの超高層ビルの屋上から飛び降りた『ダイハード』。
またマット・デイモンが白壁の建物がひしめき合うタンジールの街で屋根から屋根へ、そしてベランダへと飛び移った『ボーン・アルティメイタム』。
あるいはダニエル・クレイグがシエナの改装中の礼拝堂で敵ともみ合い、作業用の足場からロープで宙吊りになった『007/慰めの報酬』。
こうした作品の中で、私は幾度も"ジャッキー・チェン的瞬間"と出会い、高揚感に包まれます。
そしてその瞬間の記憶をたどる時、そこにはいつも『プロジェクトA』という作品があるのです。
─────────────────────────────────
●『プロジェクトA』
出演:ジャッキー・チェン、ユン・ピョウ、サモ・ハン・キンポー 他
監督・脚本:ジャッキー・チェン
製作:レナード・ホー
製作年:1984年
製作国:香港
─────────────────────────────────
1月のテーマ:はじめての○○
「ママは、お化粧した男なんて大キライ」
私がまた幼かった頃。
母親の好みにより、彼が我が家のTVに映ることはほとんどなかった。
濃すぎる化粧、長い髪、奇想天外な衣装、あごを突き出して歌う妖艶な姿。
その独自のスタイルと歌唱力で人気を博していたジュリーこと沢田研二。
ビジュアル系の元祖。
女の衣装を美しく着こなし、日本人の憧れである青い瞳をカラーコンタクトで簡単にやってのけ、まぶたに真っ青なアイシャドウを乗せた歌手。当時、目の周りを青くしている男といえば、幼い私の知る限りでは、歌舞伎役者と、進研ゼミのキャラクター・ブッチ(確か左目だけ)ぐらいなものだったな。
たまの土曜夜、『8時だョ!全員集合』が、私とジュリーとの唯一の接点であった
(我が家は「全員集合」OKの家庭だったのだ)。
渋谷公会堂の舞台の上で、持ち前の"アンニュイフェロモン"と正反対な、体を張ったおばかコントを志村けんと絶妙な間合いで繰り広げていた。躊躇するどころか、それを満喫しているかのように生き生きと演ずるジュリー。番組後半、ステージ転換で現れた彼は体中に電飾をちりばめ、なんとパラシュート背負って「TOKIO」を熱唱...。
それは衣装なのか、セットなのか。
顔の作りなんか当時の私の好みには全然合わなかったし、やることとか佇まいも現実離れしていて、ちょっとつかみどころがない。でも、この人、気になる。母の手前、無関心を装いながら、こそっとみていた。
GSからピンになり、脱アイドル路線を突き進むジュリーは、歌手としてだけでなく、役者としても多くの作品に登場していた。が、彼の出演作には、男女のきわどいからみのシーンが多かったため、うちのブラウン管からジュリーは、さらに遠ざかっていったのだ。
俳優・沢田研二を始めてちゃんと見たのは私がすっかり大人になってから。
伝説のTVドラマ『悪魔のようなあいつ』(1975)
1968年12月に発生した3億円強奪事件をモチーフとした青春劇。犯人の可門良(沢田研二)は、高級クラブ「日蝕」で歌手として働いているが実は脳腫瘍に冒されており、余命いくばくもない身体であった...。
暴力シーン、挑戦的な演出、性描写。熱狂的な人気を博したようだが、いかんせんこのジュリーはやばい、やばすぎる。周囲の人物や風景の見え方は、まあその時代相応なのだが、ジュリーは不思議と全く時代を感じさせない姿。流行廃りもない、永久保存版の魅力ってこういうことなんだなと実感する。
美しいものは、なにやっても美しく切り撮られる(樹木希林?)。鼻血をだらだらと出すシーンを見た後、彼の魅力が完全なものなんだなー、なんて確信した人は少なくないのではないか。この作品はいまだにファンが多い。
さて。ようやく今週の1本はコレ。
70年代邦画の傑作、『太陽を盗んだ男』。
しがない中学教師(沢田研二)がアパートの一室で作った原爆をエサに、国家相手に喧嘩を売る荒唐無稽な話。
退廃的なジュリーの魅力、CGナシのアクション、社会問題の投影、そしてストーリーに散りばめられた完全な「ヒーロー」たち(「ウルトラマンレオ」「鉄腕アトム」「王、長嶋」「ストーン」などなど)。
これらのエッセンスの中を、「生きる証」に向かって、それぞれがまっしぐらに突き進む姿。画面から炸裂させる作品のパワーが本当にすばらしい。
公開当時、沢田研二31歳。46歳の菅原文太。
文太も負けてない。若すぎる。かっこよすぎる。銭形警部さながらの文太の不死身っぷり。CGナシの映像なのにそれってすごくないか?
デジタル技術を駆使した昨今の映像と比較したり、時代の流れ、技術の進歩、そんな細かいところをあげていけば突っ込みどころも満載だが、それを差し引いたとしても、見応え充分の秀作!
サッカーの日本代表戦すらスポンサーがつかなくて、LIVE放映が危ぶまれる、2009年不況時代。
だからこそ、この1本を観てもらいたいなと思う。このパワーは、もはやファンタジーなのか...。
是非、「はじめてのジュリー」はまずはこの作品から。
正統な選択。今週の1本はこれで。
───────────────────────────
『太陽を盗んだ男』(1979)
147分/日本
監督:長谷川和彦
出演:沢田研二 菅原文太 池上希実子
───────────────────────────
12月のテーマ:節目
私の頭の中には、たくさんの扉がある。それぞれの扉の向こうには、色んな年齢の私が潜んでいて、ことあるごとにピョンピョン飛び出してくる。風がピューっと吹けば"風の又三郎が来たかもしれないよ"と、小学生の頃の私が扉から顔を出してくるし、肉じゃがを食べようとすると"早くしないと、お肉がなくなっちゃうよ!"と、ここでもまた、小学生の頃の私が登場してくる。つまり、私はいつだって1歳であり2歳であり、10歳であり15歳である。どの年齢の私も、私の中でずっと生き続けている...ような気がしている。
『赤い風船』を見た。ジャン・コクトーが"妖精の出てこない妖精の話"と評した短編フランス映画だ。物語は、少年パスカルが街灯に結ばれた風船と出会うところから始まる。パスカルは風船のヒモを握り、いつもと同じように学校に向かう。しかし、風船と一緒にバスに乗ろうとしたら、車掌さんに乗車を断られてしまう。パスカルはバスには乗らず、学校まで走っていくことに。なぜって、それはもちろん、パスカルは風船を手放したくなかったから。風船を大切に想う気持ちとともに、パスカルの日常は少しずつ変化していく。遂には、ヒモを握らなくても、パスカルの後ろには必ず風船が付いてくるようになる。
この作品には、ほとんどセリフがない。そこにパリがあってパスカルがいて、パスカルの後ろには赤い風船が漂っている。それだけだ。ストーリーは具体的な言葉で語られることなく、ただ、スクリーンに映し出される。そのせいか、作品をあえて言葉で説明をすることに、妙な違和感を覚えてしまう。でも、こういう説明だったら何とかしっくりくる。これは"切なくて嬉しくて悲しくて楽しい"映画だ。頭の中にいる5歳児の私が、扉をバーンと開けてダンスをし始めるような、そんな映画だ。
今年も慌しく過ぎていった。でも、私はとってもラッキーだ。ピンチに陥った時はいつも、誰かが、何かが、映画が、音楽がそこにいてくれて、感謝すべきことに気づかせてくれた。そしてこの年末、私は『赤い風船』と出会えた。私は、頭の中にいる5歳児の私との再会を楽しみながら、何回も何回も"ありがとう"と言った。
───────────────────────────
『赤い風船』
監督:アルベール・ラモリス
出演:パスカル・ラモリス
製作年:1956年
製作国:フランス
───────────────────────────