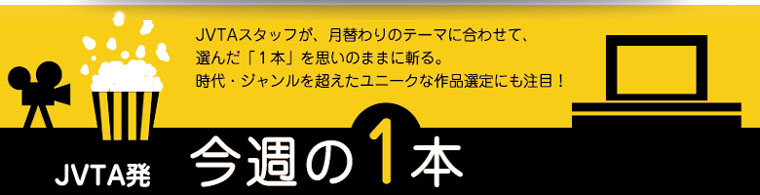vol.97 『潮風のいたずら』 by 石井清猛
12月のテーマ:息抜き
大抵の場合"息抜き"と呼ばれる行為が私たちにもたらすものは、それが身体的な観点からであれ精神的な観点からであれ、概ねポジティブなものだと考えられていますが、どうも映画の中の"息抜き"となると、話はそれほど単純でもないようです。
例えば休暇中に友人たちと訪れた山小屋で悪霊に取り付かれたり、小川のほとりで馬を休めているところをお尋ね者のガンマンに襲撃されたり、パーティーの席で豪勢な料理に舌鼓を打っている時に抗争相手のギャングにマシンガンを掃射されたりといった、およそ望ましい息抜きとは似ても似つかない災厄に見舞われる一方で、のどかなピクニックの最中にパラレルワールドに迷い込んだり、リビングで何気なく見ていたテレビ番組の世界に閉じ込められたり、早朝のカフェでくつろいでいる時に運命の人に出会ったりといった、必ずしも災厄とは限らないものの、一概に望ましい息抜きとも呼べない出来事が起きたりするのを目の当たりにすれば、誰でも一旦は「どうやら映画の中の息抜きというのは一筋縄ではいかないらしい」と納得する以外にないでしょう。
果たしてゴールディ・ホーン主演のロマンティック・コメディ『潮風のいたずら』で私たちが目撃するのも、そのような"一筋縄ではいかない息抜き"の顛末といえます。
のちに『プリティ・ウーマン』や『プリティ・プリンセス』を撮ることになるゲイリー・マーシャルがこの作品で描いたのは、それはもう、あきれるほど突拍子もなく、あり得ないほど楽天性に満ちた、実に映画的な息抜きでした。
大富豪のジョアナとその夫グラントは豪華ヨットでの気ままな船旅の途中小さな港町エルク・コーブに立ち寄る。そこで船室のクローゼット改装のためジョアナに呼ばれた地元の大工ディーン。どケチで性格ブスのジョアナは報酬も払わず悪態をつきまくり、挙句にディーンを海に突き落とす。クルーザーが港を離れたその晩、ジョアナは足を踏み外して落水。彼女はエルク・コーブに流れ着いて救出されたもののショックで記憶をなくしていた。ニュースを見たディーンは復讐のため夫と名乗り出てジョアナを引き取ることを思いつく...。
巨大なクルーズ船での贅の限りを尽くした船旅という常識をはるかに超えたスケールの息抜きは、それでも他の息抜きと同じく映画の法則に従って無慈悲にも中断され、やがてジョアナは"4人の息子を持つ妻(と見せかけたメイド)"としての生活を強いられることになります。
映画の前半で描かれるその生活の過酷なディテールはほとんどブラックユーモアに近く、「何かがおかしい」と感じながらもディーンに言いくるめられ、渋々家事を続けるジョアナの徹底的な不適合ぶりに、恐らくフェミニストもアンチフェミニストも、女性も男性も、笑うのを忘れて静かに胸を痛めるほかありません。
ディーン役のカート・ラッセルはこの前半において男性原理の非道な暴走ぶりを見事に演じ切り、見る者に軽い戦慄を与えます。彼が『デス・プルーフ』でタフな女子に袋叩きにされなければならなかった理由はこの映画にあった、と確信する人が出てきてもさほど不思議ではないでしょう。
いずれにしても、ディーンはこのように容赦なくジョアナを利用することで格好の息抜きの機会を得るわけです。
ただそれが決して一筋縄ではいかないのは、皆さんご承知のとおり。
慣れない家事をロボットのようにこなす毎日にあやうく心神を喪失しかけながらも、ジョアナは持ち前のタフでスマートでキュートな性格を発揮し、徐々に4人の息子と夫の心をつかんでいくのです。
アイデンティティ・クライシスの只中で魂を抜き取られたかのように終始虚ろな目をしていたジョアナが、ある瞬間についに生き生きと輝き始める場面はまさに霧が一気に晴れるような爽快さで、(当時の)"ロマコメの女王"ゴールディ・ホーンの面目躍如といえます。
それがでっち上げられたものとも知らず、新たに与えられたアイデンティティをすっかりその気で受け入れて"わが道"を進み始めるジョアナ=ゴールディ・ホーンの姿は、一挙手一投足がいちいち笑えてかつ最高に魅力的です。
やがて自分の息抜きが一筋縄でいかないことに気づくディーン=カート・ラッセルでなくても、きっと彼女から片時も目が離せなくなってしまうことでしょう。
さて映画の終盤近く、ディーンの息抜きが突如として中断されたあと、2人(+4人)に何が起こるのでしょうか?
その『プリティ・ウーマン』も色あせるほど楽天的で突拍子もないエンディングは、皆さんどうかご自分で確かめてみてください。
最後におまけ情報を1つ。
『潮風のいたずら』を緩やかな原作として変則リメイクされたのが韓国ドラマの『ファンタスティック・カップル』です。
私はまだDVDのDisc1しか見ていませんが、主演のハン・イェスルの性格ブスっぷりは本家ゴールディ・ホーンを上回っていたかもしれず...。
─────────────────────────────────
『潮風のいたずら』
監督:ゲイリー・マーシャル
製作:アレクサンドラ・ローズ、アンシア・シルバート
脚本:レスリー・ディクソン
撮影:ジョン・A・アロンゾ
音楽:アラン・シルヴェストリ
出演:ゴールディ・ホーン、カート・ラッセル、マイケル・ハガティ、
エドワード・ハーマン、キャサリン・ヘルモンドほか
製作年:1987年
製作国:アメリカ
─────────────────────────────────